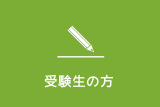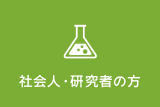沿革
本学の植物園は、盛岡高等農林学校の創立(1902年)以来、その敷地の東南部に設置され、1905年(明治38年)に現在教育学部が建っている地域北側に移転した。1974年(昭和49年)に大学の整備拡充にともない盛岡高等農林学校の創立当時の植物園・樹木園・校舎敷地 を合わせた現在地へ移転した。
設置目的
植物学、農学、森林科学、動物学、園芸学、造園学などの研究教育のために設置され、国内外の植物を収集植栽し、また自生種を保護管理している。植物園は、野鳥・昆虫・植物など、動植物の共生系モデルとして、これらの観察や保護、研究試料の提供と学生の教育研究の場として利用され、さらに一般市民にも開放している。
概要
植物園として設置以来、90数年の長い年月を経過しており、盛岡市内では稀少な高木樹林の緑地を形成している。その中で、横に広がって美姿の“山辺の松”、どっしりとそびえる“目時の杉・ひば”は、いずれも南部藩家老屋敷の頃からの古い時代のものである。この植物園の大きな特徴の一つは、多数の植物種に占める外国原産樹木の比率の高いことで、現在、137科、530属、約800種以上の植栽種・自生種が生育しており、面積は、約49,500㎡ある。なお、園内には平成6年に重要文化財に指定された農学部附属農業教育資料館(旧盛岡高等農林学校本館)がある。
園内の構成
1.自啓の森
旧盛岡高等農林学校学生寮“自啓寮”跡地に、郷土森林生態観察モデル林として1985年に造成された。①アカマツ-コナラ群落、②コナラ-クリ群落、 ③ブナ-ミズナラ群落、の3ブロックで構成され、一偶に“自啓寮跡”の記念碑が建っている。
2.池・水生植物展示圃
池は1980年に「破砕転圧工法」(旧農業土木学科内、農地造成研究会の考案による)で造成された「土池」で、規模は面積1,350㎡、水深0.2-1.2m。特徴は漏水の少ないことである。夏季にはスイレンが美しい。 水生植物展示圃は面積600㎡で、ジュンサイ、ハナショウブ、カキツバタ、ショウブ、ヒメカユウなどが生育している。
3.鈴木梅太郎と宮沢賢治の碑
1983年に元教授と卒業生の両偉人を顕彰して化学実験棟跡に建てられ、この小高い丘の北の裾にはメタセコイヤ(卒業生の三木茂博士による化石発見、命名)がそびえる。
4.読書園
初夏にボタン、シャクヤクが美しく咲き競う。この南の一偶に本植物園のシンボル“山辺の松”が静座し、入園者たちを厳粛な学園気分にひき込む。
5.日時計
“ポランの広場”の一偶に設置されている。日時計と説明板は、宮沢賢治が愛用した楽器(チェロ)と譜面台の関係を模倣したものである。日時計は太陽による標柱の影を文字盤で読み時刻を計るもので、水平面の大環は水平型日時計の文字盤、また凹型半球内の横帯は赤道面に平行し、赤道環日時計の文字盤からなる「二重日時計」である。盛岡太陽時を基準として作られているため、常用時(明石)との時差として-25分と均時差による補正が必要である。
農学部附属植物園の利用について
[利用申込み]
グループで植物園見学・利用、研究(試料採集を含む)など希望する場合は、【植物園使用願(PDF)】に必要事項を記入の上、あらかじめ農学部事務室 (Fax:019-621-6107 E-Mail:asomu@iwate-u.ac.jp )に申込み下さい。E-mailの場合、本文に直接必要事項の内容を記載いただいても結構です。
[利用上の注意]
園内に設置してある掲示板に記載された注意事項を守って下さい。特に、植物園としての自然環境を保全するため、園内への車の乗り入れ、園内での犬の散歩、喫煙、球技、スケートボード遊びなどは、禁止しています。ゴミ入れは設置していないので、飲食などの後、可燃・不燃ゴミは、各自持ち帰るよう、お願いします。
お問い合わせ
岩手大学 農学部 学部運営グル-プ
〒020-8550 岩手県盛岡市上田3丁目18-8
TEL:019-621-6103
Email asomu@iwate-u.ac.jp