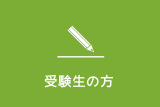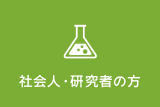動物栄養学研究室(動物科学・水産科学科)
- 所属教員
- 牧野 良輔
- キーワード
- 動物 家畜 環境 生命科学 産業動物 食と健康 食料・食品
研究内容
栄養・飼料の面から家畜の生産性を向上する
動物栄養学研究室では、ニワトリを中心とした動物の栄養に関する研究を行っています。大きく分けると①新規飼料原料の探索と開発、②栄養素の代謝と機能解明、③タンパク質代謝の評価という視点から研究に取り組んでおり、ニワトリを飼育することはもちろん、細胞の培養、遺伝子やタンパク質レベルの解析も行います。分子、細胞、臓器から個体まで、さまざまな階層の研究を通して、家畜の生産性向上に取り組んでいるところです。
①新規飼料原料の探索と開発
日本の飼料自給率は飼料全体の3割以下であり、特にトウモロコシや大豆粕などの濃厚飼料の自給率は極めて低い状況にあります。飼料費が畜産農家の経営コストに占める割合はウシで30〜50%、ブタやニワトリは50〜60%と高く、飼料費の削減が求められています。さらに世界情勢によっても飼料価格は変動するため、安価で安定的に供給可能な国産飼料原料の探索と新規飼料の開発が必要です。食品加工等で生じる加工残渣など多くの未利用資源が残されており、それらは有用な栄養成分を含んでいることもあります。一方で、未利用資源を飼料化する場合、水分含量が高く腐敗しやすいことなどの問題点を抱えていることも少なくありません。また、成分上は飼料として有用であると思われても、家畜の嗜好性や有用成分の吸収率が低いなど、実際には利用できないことも考えられます。そのような飼料特性を明らかにするためには、実際に飼料を調製しニワトリを飼育する飼養試験が必要であり、当研究室では実際にニワトリを飼育して出口を見据えた新規飼料原料の探索に取り組んでいます。
②栄養素の代謝と機能解明
ニワトリが摂取した栄養素は消化・吸収を経て体内へと取り込まれた後、多くの場合他の物質(代謝産物)へと変換されて利用されます。しかしながら、それらの栄養素がニワトリの体内でどの程度代謝されるのか、またそれらの代謝産物は体内でどのように機能しているのかについては、未解明の点が多く残されています。特に注目しているのは、糖とその代謝物です。ニワトリを含む鳥類は他の哺乳類と比べて高血糖な動物です。そのため、糖由来の代謝物が他の動物種よりも多く存在すると思われますが、それらの機能はまだまだ謎が残されています。当研究室では質量分析装置等を用いて、ニワトリ体内にある代謝産物の定量解析を行うことに加え、ニワトリ細胞を用いて代謝産物の機能解明などを行っています。
③タンパク質代謝の評価
家畜は、栄養価値の乏しい土壌で栽培できる作物や、ヒトにとって栄養バランスがあまり良くない植物性タンパク質を飼料にして、良質なタンパク質を供給してくれる重要な食料源です。一方で、飼料として摂取したタンパク質を畜産物(肉・卵・乳など)に変換する効率が悪くては、経済的にも環境的に余分な負荷がかかります。当研究室では、いかにして家畜が効率よく飼料由来のタンパク質を畜産物へと変換できるかを研究しています。そのために、タンパク質代謝を正しく評価することが重要です。飼料から摂取したタンパク質は消化管内で消化されてアミノ酸となり、吸収されたアミノ酸は体内で再度タンパク質へと合成されます。一方で、体内のタンパク質は絶えず分解もされています。このタンパク質の合成と分解のバランスによって、家畜のタンパク質蓄積量が左右されます。この合成と分解を正しく評価することで、効率の良い畜産物生産を考えることができるのです。そこで当研究室では、同位体という「重い」化合物を使うことで、骨格筋などのタンパク質代謝回転速度を評価しています。飼料中の栄養素や飼育環境など様々な要因により、タンパク質の代謝は変化します。どのような要因がタンパク質の蓄積量を増やすのかを明らかにすることで、効率の良い畜産物生産を目指しています。