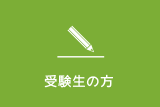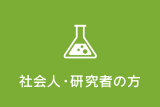研究内容
岡田啓司(教授:生産獣医療学)
(1)アニマルウェルフェア(家畜福祉)に基づいた家畜群管理に関する研究
家畜の生活の質(QOL)を向上させることによって生産性の向上する可能性のあることを、世界獣疫事務局(OIE)は宣言しています。この考えに基づいて、家畜のQOLを高めて病気を出さず、生産性を向上させる手法を研究しています。具体的には血液による栄養診断(代謝プロファイルテスト)や、加速度センサによる牛の異常行動摘発など、大規模牛群管理の基礎となる研究を行っています。また家畜のQOLの基本となる護蹄管理の研究も行っています。研究フィールドは岩手県内と北海道(十勝、釧路)です。

家畜検診車


北海道の放牧牛 実験中のセンサをつけた牛

加速度センサによる牛の管理モニタ
(2)福島原発事故に関わる低線量持続被曝牛に関する研究
福島第一原子力発電所事故後、旧警戒区域内に生き残った牛180頭について、低線量放射線持続被曝の影響評価の調査を行っています。大型哺乳類の被曝実験は、事故が起きなければできないことであり、貴重な情報が得られています。研究フィールドは福島県の浪江町と大熊町です。
高橋正弘(准教授:臨床獣医学、獣医繁殖学)
(1)牛胚の品質と血中脂肪酸濃度の関係
(2)バイパス脂肪酸投与が卵子品質ならびに胚発生能力に与える影響
近年、欧米先進国をはじめとして、わが国でも牛における受胎性が年々低下しており、国際的な問題となっています。この牛の受胎率低下の要因については、いまだ明確に解明されていません。そこで雌側の要因、すなわち血清中の脂肪酸濃度と卵子品質・胚発生の関連性を調べ、卵子や胚に与える影響を詳しく解析することにより、牛の受胎率低下の原因を探っています。また、バイパス不飽和脂肪酸が過剰排卵処置、周産期に与える影響を解析し、受胎率向上の対策に役立てることを研究の目的としています。

牛の受精卵


採卵風景 卵巣の超音波画像